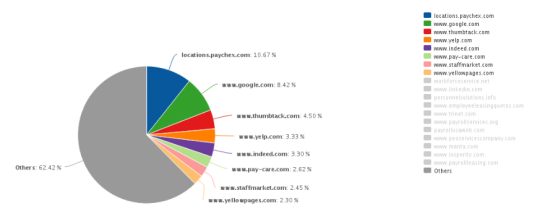アフィリエイトなどのインターネット広告サービスを運営するインタースペースでは、サイト運営者様向けにサイト内情報の絞り込み検索機能のプラグインを提供しています。
アフィリエイトサイトの運営において、重要なポイントの一つが「いかに成果につながるユーザーを多く集客するか」という点です。SEO対策なのか?リスティングでの集客なのか?ソーシャルメディアを使うのか?そんな集客の悩みに応えるサービスが『SELEKiT』です。
Googleなどの検索エンジンで上位表示されやすい条件は、数百項目あるといわれていますが、その1つはコンテンツが「良質」であることだといわれています。つまりユーザーが必要としている情報を発信しているサイトを作ることが重要です。
多くのユーザーが訪れ成果が多く発生しているサイトには必ず、ユーザーが必要な情報を自分で検索できる機能が備わっています。しかし、サイト運営者がサイト内に絞り込み検索機能を追加するのは、工数も費用もかかり決して容易ではありません。『SELEKiT』は、すべてのサイトに絞り込み検索機能を安価で簡単に追加することができます。
Clik here to view.

『SELEKiT』を導入することによってサイトはユーザーに必要な情報を的確に提供することができ、求めていた情報にたどり着いたユーザーはサイトに滞在する時間が長くなります。滞在時間が長いサイトは検索エンジンから「良質」なサイトだと判断されやすいと言われていますので、検索エンジンで上位表示されやすくなり、成果がより多く発生するようになります。『SELEKiT』は、サイト運営者にとっても、ユーザーにとってもWin-Winの関係を築けるサービスです。
インタースペースはこれからも、広告主様、お客様、アフィリエイトパートナーから信頼頂ける商品開発を続け、サービスの質とWin-Winの関係性を追求してまいります。
▼クロスフィニティ考察
アフィリエイトプロモーションにおいて、広告主が質の良いユーザーの獲得を増やす施策は多岐にわたります。中でもGoogleなどの検索結果に表示されたアフィリエイトサイトに広告掲載することや、そのアフィリエイトサイトの中でも、掲載位置を上位にすることが主流となっています。その結果、広告主はアフィリエイトサイトへ競合他社よりも高い報酬単価を提示する事になります。
特定の有力アフィリエイトサイトになると、広告掲載することを希望している広告主は多く、複数の広告主が競うようにアフィリエイトサイト側へアプローチをかけるため、有力アフィリエイトサイトに掲載するための報酬単価は、高騰し続ける事になります。そのため、報酬単価がまだ高騰していない新たなアフィリエイトサイトが増えていくことを広告主は期待しています。
今回、ご紹介するインタースペースの『SELEKiT』は、そのような広告主の期待に応えることが可能になるかもしれません。アフィリエイトサイトは、検索結果で上位に表示されるように、SEO対策やリスティング出稿を積極的に行っておりますが、『SELEKiT』は、そのGoogleAdwordsの出稿をサポートする事が出来るからです。
『SELEKiT』は有力なアフィリエイトサイト内でよく見られる、「絞り込み機能」を安価で簡単に追加できるサービスです。これにより、大小いろいろなアフィリエイトサイトが、絞り込み機能を採用しやすくなります。絞り込み機能の設置は、GoogleAdwordの出稿においての要件の一つとなっているため、出稿時の審査に通過しやすくなります。
その結果、新たなアフィリエイトサイトが、検索結果の上位に表示される可能性も広がり、報酬単価が高騰しないうちに掲載ができれば、低単価で質の良いユーザーを獲得することが可能となります。
また、今までとは異なる新たなコンテンツを持ったアフィリエイトサイトに掲載がされるので、広告主のウェブサイトへ流入するユーザー層にも変化が起こるかもしれません。
【補足】
有力アフィリエイトサイトの上位に掲載させる施策は、報酬単価を高く設定するだけではありません。
クリックやアフィリエイト成果が発生しやすいかという基準も評価対象の一つとなり、アフィリエイトサイト内での掲載位置が決定されている場合も増えています。
そのため、広告主はウェブサイトのユーザビリティを見直し、コンバージョンレートを上げるCRO施策も合わせて行うことが重要になっています。
クロスフィニティでは、弊社ホームページのコラム内に、広告主のウェブサイトのコンバージョンレートを上げるCRO施策やSEO施策の事例を紹介しています。
合わせて、こちらもご一読ください。