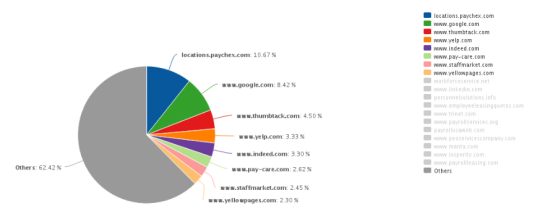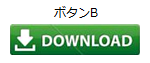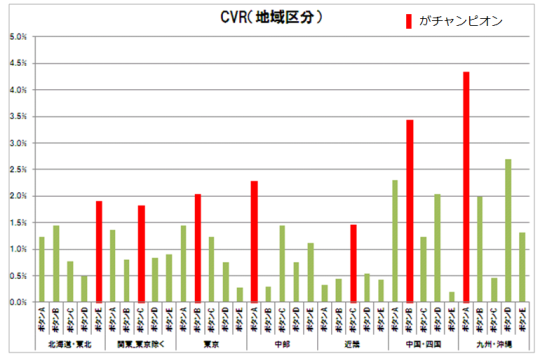モバイルファーストインデックスの導入へ向けて、日々数多くのニュースが飛び交っています。今回はseoClarityミト・ガンジー氏が注目している業界識者のコメントについて、同社のブログ記事からご紹介します。
—
皆さんにも同意していただけると思うのですが、重要な割に、私たちにとってGoogleのモバイルファーストインデックスは未だわからないことだらけです。
確かに少なくとも公式にはそういった状況です。大元の発表内容やネット上で広まっている情報は数多くあるものの、いまだ明確なガイドがない状態です。
幸いにも、SEO業界界隈は新しいインデックスの影響を予測することに対し積極的でした。今回の記事では、モバイルファーストインデックスについて、業界リーダーたちが予測したことや発見したこと、また、それらが私たちの日々の仕事に及ぼす影響についてまとめました。自社のサーチビジビリティに対しこの変化が何を意味するのか、皆さんも関心を持っているところではないかと思います。
そもそもなぜ、モバイルファーストなのか?
Googleの2011年「新しいマルチスクリーンワールド:クロスプラットフォームの消費者行動の理解」レポートの締めくくりは
「スマートフォンは、日々メディアを利用する上で非常に重要なものとなっています。スマートフォンは一日の中で最も多く使用されているデバイスで、複数の画面にまたがる活動の最も一般的なスタート地点となっています。そして、Google モバイルはビジネス上、不可欠なものとなっています。 」
といった内容でした(太字の強調は筆者によるもの)。
当時、多くの人が検索結果ページの設計を最も参考にしていましたが、私はGoogleのこの発表をモバイルユーザーに焦点を当てていく初期の兆候と捉えていました。
2年後、Googleはモバイルユーザービリティレポートをウェブマスターツールに追加し、1か月後には検索結果ページに「モバイルフレンドリー」のスニペットを導入しました。そのあとはご存知の通りです - モバイルフレンドリーに関するアルゴリズム更新、モバイルマイクロモーメント、AMP など…
iPullRank(※)社長マイク・キング氏が書いているように、
「ブランドサイトでは、スピード、構造化データ、モバイルフレンドリーに焦点を当てるべきです。 Googleが最近進めてきたことは、結局全てこれら3つの事柄に集約されます。」
そして今、モバイルページをPC版のページよりも優先させるインデックスの完全な実施が間近に迫っています。既に判明していることに注目しましょう。業界のリーダーたちが考えている事柄は、変更後に順位に影響を与える重要な要因となります。
※iPull Rank社 : 米国・ニューヨークのデジタルマーケティングエージェンシー
モバイルファーストインデックスはGoogle の現在のインデックスにとって代わる
新しいインデックスが検索順位に影響を与えることは明らかです。そこに疑問の余地はありません。
distilled社(※) 創業者兼CEOウィル・クリッチロウ氏は新しいインデックスの潜在的な重要性について、以下のようにまとめています:
「これが何を意味しているかにもよりますが、モバイル経由のトラフィックをあまり得られていない企業や、モバイルサイトの利便性にあまり注力していない企業であっても、モバイル版とPC版サイトのパフォーマンスに重大な影響が及ぶ可能性があります。」
これは至極当然のことでしょう。
※distilled社 : 英国・ロンドンに本拠を置く、オンラインマーケティングエージェンシー
まず、Googleのゲイリー・イリェーシュ氏によると、この新しいインデックスは現在の検索エンジンの設定のかなりの部分を置き換えていくと想定されることが ― PCの結果をモバイルユーザーに表示するのではなく、PCで検索している人にモバイル結果を表示するようになる ― 少なくともこのツイッターのやりとりから明らかになっています(Hubspot経由で発見されました)。
フィル・クック氏のツイート
「@methode ½ 当初2つの個別のインデックスがあるとおっしゃっていましたが、現状ではモバイルのシグナルに基づく1つのインデックスになるということでしょうか?」
「@methode 2/2 ・・そしてPCのユーザーにもモバイルの検索結果ページが表示されるということですか?基本的には今あるものと入れ替わるということ?」
ゲイリー・イリェーシュ氏のツイート
「その通り、現在のものと入れ替わります。」
ジョン・ホッグ氏のツイート
「@methode 逆になるだけで、同じ問題が生じてしまわないですか?」
ゲイリー・イリェーシュ氏のツイート
「PCよりもモバイルユーザーが多いため(そして急速に伸びている)、そうは思わないですね。」
(上記ソース:https://blog.hubspot.com/marketing/mobile-first-google-index#sm.000nr403d19icerku6w2nhvrxvtkr )
ここから、PCとモバイルに関して別々のインデックスが存在しないことも分かります。今回のアップデートは、評価基準をPCに関する内部項目からモバイルのものへと移行するものとなっています。つまり、モバイルページについて最適化を図っていくことが重要になるのです。
seoClarityを使えば、モバイル検索でのビジビリティを最適化できます。seoClarityはユーザーが実際に見るのと同じように、検索エンジンへのクエリに基づく結果を表示し、正確なモバイル順位情報を提供します。
そして次の問題。
Google はモバイルコンテンツをもとにサイトをランク付けする これまでは、PC向けコンテンツで対策を行ってきました。しかし、いったん新しいインデックスが完全に適用されると、もはやそうした状況は一変します。
Vetters
Agency(※) 創業者兼CEO クリスティン・シャヒンガー氏がサーチエンジンジャーナルにおいて指摘したように
「(中略)あなたのサイトの検索順位を決める際に、PCを使っているユーザーに対してもモバイル版のコンテンツが使用されます。コンテンツだけでなく、SEOに関するシグナルのほとんどが、PCからモバイルのみへと切り替わります。
※Vetters Agency社 : 米国・ラスベガスに本拠を置くSEO・オンラインデジタルマーケティング会社
つまり、PC とモバイルのサイトが別々の場合、 特にモバイルサイトのコンテンツの量が少なかったり、異なる場合は、新しいインデックスの影響を受ける可能性が高くなります 。
しかし、自社サイトがレスポンシブサイト(またはモバイルとPCのページが同じ)である場合は、問題にはならないでしょう。
「もし自社のモバイルページがPCと同じ場合、そのサイトは問題なし。 @methode #Pubcon」
(上記ソース
:https://www.blueglass.co.uk/blog/84-things-learned-at-pubcon-2016/?blu=LjPrf5 )
しかし、あなたがm.などのモバイル用のサブドメインを利用している場合は、予防的に、モバイルコンテンツについてPCと同様(もしくは近い形で)の最適化がされているか確認することをお勧めします。
考えるだけでなく、実際にページを見直すことも大切です。スキーママークアップタグや内部リンクをチェックして、両者で同じ最適化レベルを確保します。
この点について、seoClarityのユーザーであればseoClarityの持つクローラーを使用して、サイトの状況に関するテクニカルなSEO調査を行うことができます。そして、両方のページを見比べ、データが示す改善点を踏まえて最適化を行うことができます。
ラッキーなことに、モバイルUX で順位が下がることはない[ 確認済]
モバイル用のページを最適化する際の課題は、はるかに小さなスクリーン面積しかないことです。もちろん長いページを作成することもできますが、最終的にそれがユーザーに対して必ずしも良いものになるかどうかは分かりません。
では、どういった対応策がとれるでしょうか?例えば、様々な項目をアコーディオンやその他UX エレメントの背後に隠し、必要な時だけユーザーがアクセスできるようにできます。
幸いなことに、ゲイリー・イリェーシュ氏も認めているように、例えばアコーディオンを利用した隠しコンテンツや、他のデザイン手法によってモバイルページを最適化しユーザーエクスペリエンスを向上させることは、検索順位には影響しないのです。
クリスティン・シャヒンガー氏のツイート
「@methode PCコンテンツにおけるアコーディオンのようなページ要素は評価が下がるかインデックスされません。モバイルコンテンツのクロールについても同じ事が言えますか?」
ゲイリー・イリェーシュ氏のツイート
「@schachin いいえ、もしモバイルファースト的なコンテンツがUXの観点で隠されている場合、フルで評価されるでしょう。」
(上記ソース: https://ignitevisibility.com/google-crawling-mobile-first/ )
さまざまな長さのコンテンツを制作する必要は?
ゲイリー・イリェーシュ氏は、モバイルファーストランキングはモバイルコンテンツに基づくものと認めました。つまり、もしモバイルページの情報量が少ない場合は、検索結果順位に影響します。推測ではあるものの、Geek Powered Studios社(※) SEOディレクター ジェシー・マクドナルド氏は有用なポイントを指摘しています:
「(中略)インデックスの変更について、SEO担当者はモバイルユーザーが何を見ているかという観点から、サイト上のコンテンツを考える必要があります。これが意味することは、SEO担当者がよりコンテンツ量の少ないページについて考えていくことになる、ということです。SEO担当者は、検索アルゴリズムを満足させつつ、ユーザーの問いに最も良い答えとなるようなものを見つけ出す、といったことを始めなくてはなりません。これは医師が「控えめにすることでより大きな成果を挙げる」アプローチを取るような形でページビルディングを行うというもので、おそらくSEO史上初の出来事ではないでしょうか。」
※Geek Powered Studios : 米国・テキサスに本拠を置くSEOエージェンシー
ジェシー氏は、Googleのモバイルファーストインデックスにおいて、検索順位を維持するためには、コンテンツへのアプローチを再考する必要があるかもしれないと示唆しています。Googleに対し関連性の高いシグナル(キーワード、レイテント・セマンティック・インデクシングなど)が含まれるようページの長さを伸ばす代わりに、以前よりも少ない文字数で品質を高める必要があります。
コンテンツ制作に重大な影響をもたらす興味深い概念ではないでしょうか。
AMPは新しいインデックスではモバイルと同じではありません
ショッキングではないでしょうか?
私たちは既にAMPを利用していますが、GoogleはAMPをモバイル版コンテンツとして扱わないことを既に認めています。
マイリー・オイェ氏やゲイリー・イリェーシュ氏は、皆さんのサイトにPCとAMP版のコンテンツがある場合、モバイルファーストインデックスではAMP版を無視し、代わりにPC版をインデックスすることを認めています。
ジェニファー・スレッグ氏のツイート
「ということで @maileohyeはPC版とAMP版がある状況では、GoogleはPCをモバイルファースト用にインデックスすると認めました #StateofSearch」
(上記ソース:https://www.seroundtable.com/google-amp-desktop-mobile-first-index-23009.html )
ゲイリー・イリェーシュ氏のツイート
「@rustybrick @maileohye @AlanBleiweiss デフォルトのamp設定ではPC版が選択されます。でも、PCとampしかないサイトを見たことはありませんけど。」
(上記ソース:https://www.seroundtable.com/google-amp-desktop-mobile-first-index-23009.html )
唯一の例外は、既存のモバイルページに対するAMPページを作成し、そのAMPが掲載された場合です。
ゲイリー・イリェーシュ氏のツイート
「@rustybrick @maileohye @AlanBleiweiss そうだね。もしampがモバイル版に対して作成された場合は、ampが選択されるはず。」
(上記ソース:https://www.seroundtable.com/google-amp-desktop-mobile-first-index-23009.html )
さて、今後はどうなるのでしょうか?
私たちはモバイルファーストインデックスの影響が完全に明らかになるのを待っている状況です。しかし、ウィル・クリッチロウ氏は興味深い点を指摘しています
―
将来的に、モバイルのみからなるインデックスが登場することがあるのだろうか?と。
ウィル氏は、モバイルファーストインデックスが落ち着いた段階で、Googleはモバイルのリンクに対するクロールを開始する可能性があると推測しています。リンク指標についてモバイルのクロールを開始すること自体は大したことではありません。
しかし、彼が指摘しているように
“モバイルとPCのリンクに関する状況が同一になるまで、そうしたことはなさそうです。貴重なデータを捨ててしまうことに他ならないですから。しかし、やがてはそうなるのではないかと思っています。長期的に見て、二重にクロールをかけ続ける必要はあまりないですからね。”
—
今回の記事は当社と業務提携をしているseoClarity社の記事
「WHAT WE KNOW ABOUT THE MOBILE-FIRST INDEX (INSIGHTS FROM INDUSTRY
LEADERS)」をもとに翻訳・再構成したものです。
http://www.seoclarity.net/mobile-first-index-insights-industry-leaders-16198/
クロスフィニティは海外SEO情報ネットワークを強みに